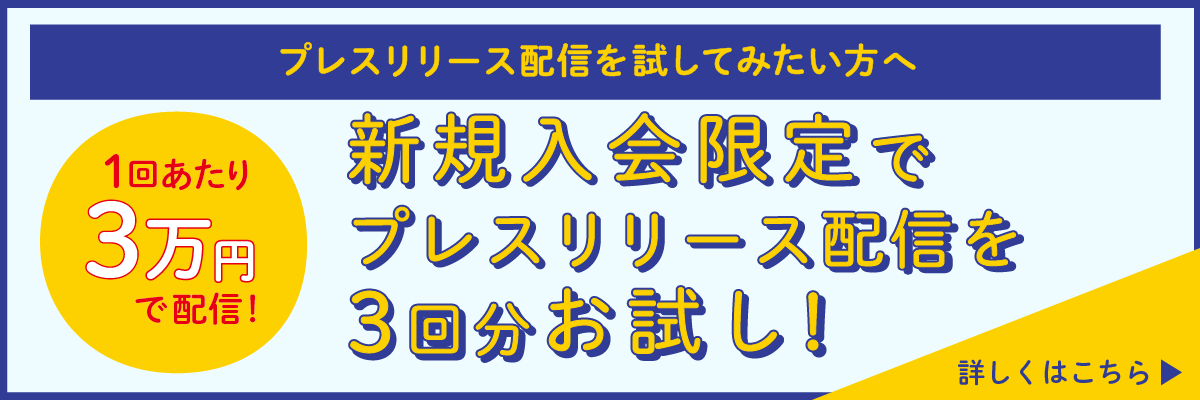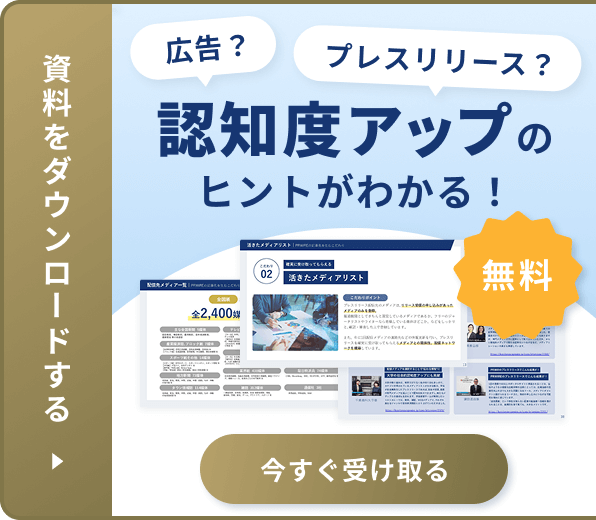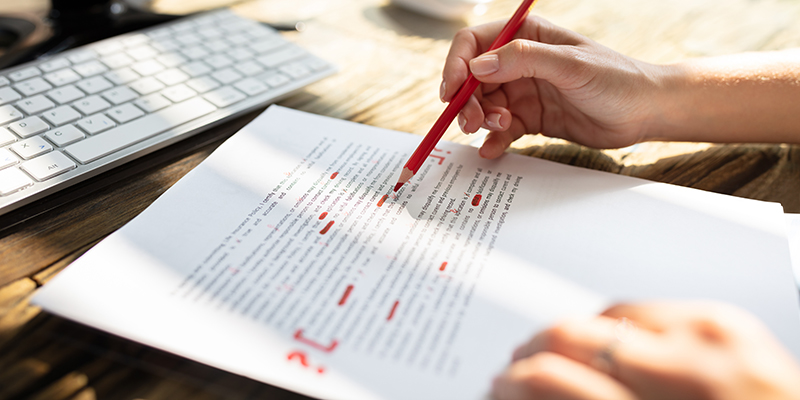
広報物において、情報の補足や著作物の信頼性を高めるため「転載」を行うことがありますが、転載には許諾が必要です。
転載の方法や注意点、引用との違いなどを詳しく解説します。
「転載」(原文転載)とは

「転載」とは、他者の著作物などを複製して、別の場所に掲載することです。
プレスリリースの場合では、自社が公開したプレスリリースがそのまま他社の著作物やWeb上に掲載されることを「転載」と言います。また原文がそのまま掲載されるため「原文転載」とも言われます。
「転載」と「引用」の違い

「転載」と「引用」は、「他者の著作物を複製し、別の刊行物や場所に公開すること」という意味では同じですが、法律の視点で見ると違います。ややこしい「転載」と「引用」の違いをそれぞれ説明していきます。
「引用」とは
「引用」とは、自分の文章を補足したり根拠を示すため、他者の著作物(文章、図、画像、表など)を副次的に紹介し掲載することです。
「転載」との違いは、自分の著作物に対する他者の著作物の割合です。
引用する他者の文章量が自分の著作物より少ない場合、つまり自分の文章の方が割合として多い場合、引用となります。
引用について、下記の記事内でもまとめています。あわせてご確認ください。
「プレスリリースはどこまで引用OK?広報とメディアが知りたい引用と著作権のルール」の記事を見る
転載と引用は主従関係により違う
転載と引用の関係を表すと、下記のようになります。
■転載と引用の違い
- 転載:自分の著作物<他者の著作物(自分の文章の割合の方が少ない)
- 引用:自分の著作物>他者の著作物(自分の文章の割合の方が多い)
ただし、文章量において「他人の著作物がどれくらいの割合を占めると転載」という明確な基準はないため、あくまでも各自の判断となります。覚えておきましょう。
転載を行う際の注意点

転載をする際には、下記の注意が必要になります。それぞれ説明していきます。
転載には著作権者の許可が必要
転載の際は、著作権者の許可が必要です。
全ての著作物は、著作権法により守られています。許可を得ていない掲載の場合、複製権(著作財産権の一つで、著作物を無断で複製する権利のこと)を侵害する「無断転載」となってしまいます。
許可を得る際には「転載する著作物の範囲や目的」「転載先」「転載する方法」の3つを明確にして許可を得ましょう。これらが守られていない場合、許可が下りないこともあります。
「自分と他人の文章量が、このくらいの割合を占めると転載」という明確な基準がないため、転載か引用か迷う場合もあるでしょう。迷った際は、著作権者に許可をとることをおすすめします。
また転載ではなく引用の場合は、引用の要件を満たしていれば著作権者の許可は不要です。
原文の出典を明記
転載のもう一つのルールは、掲載する文章の出典を明記することです。
原文がWebページの場合は、該当ページへの外部リンクを必ず設置しましょう。例えば下記の表記があると良いでしょう。
- Webページの場合……著者名、ページタイトル、サイト名、URL
- プレスリリースの場合……企業・団体名、発信日、タイトル、URL
※学会誌や学術誌から転載する場合、別途記載方法の規定がある場合があります。各ホームページなどで確認してください。
ただし「無断転載不可」の表示がある場合は転載することはできません。また転載する際は転載元の表現(原文)を変えてはいけません。これらは引用の場合も同様のルールです。再転載もNGです。覚えておきましょう。
転載の許可を取る必要がないケース
以下の3つに該当する場合、転載の許可を取る必要はありません。
- 国等の周知目的資料(著作権法32条2項)
- 新聞・雑誌に掲載された時事問題に関する論説(著作権法39条1項)
- 公開して行われた政治上の演説・陳述・裁判手続(著作権法40条1項)
ただし「転載禁止」の表示がある場合はこの限りではありません。覚えておくと役立つでしょう。
自社プレスリリースが転載されるメリット

インターネットの発達に伴い、自社が発表したプレスリリースがそのまま転載される機会も多くなってきました。自社のプレスリリースが転載されるメリットは2点あります。それぞれ解説します。
転載先を通して幅広いリーチを獲得できる
さまざまなサイトやWebメディアにプレスリリースが転載されれば、自社広報部だけでは広げられなかった範囲の人々に対する接触機会を増やすことにつながります。より幅広く、より多くの生活者へのリーチが獲得できます。
また、社会的信頼性や知名度の高いWebメディアに転載されれば、転載元である自社の信頼性や認知度も高まるでしょう。SEO的にも、転載元としての評価が高くなる可能性があります。
自社サイトのアクセス増により認知度向上が期待できる
転載されたプレスリリースの転載元リンクがクリックされれば、自社サイトへのアクセスが増えることになります。自社サイトへのアクセスが増えれば、さらなる企業認知や商品認知の向上が期待できます。
また、転載先では記載しきれなかった詳細情報や、その他の商品・サービス情報にも触れる機会が増えることになり、興味や関心を深めてもらえる可能性があります。
転載先からの流入増を無駄にすることなく、企業ブランドや商品コンテンツのページへのナビゲーションを整備するなどして、さらなるPR効果の向上につながるようにしておくと良いでしょう。
プレスリリースのメディア転載
プレスリリース配信会社を経由してプレスリリースを配信すると、配信会社の提携先であるWebメディアのニュースサイトやポータルサイトなどに、自動的にプレスリリースが転載されます。例えば当社では、約70のWebサイトと提携し、内50サイト以上に配信した全プレスリリースが転載される仕組みになっています。
プレスリリースを確実に広めたい、より多くの生活者に知らせたいという広報担当の方は以下をご検討ください。
共同通信PRワイヤー「国内プレスリリース配信サービスのご案内」のページを見る
またプレスリリースの転載を検討中のメディア関係者の方はこちらをご覧ください。
「メディア提携のご案内」のページを見る
自社プレスリリースが転載された時のチェックポイント
プレスリリースなどの自社情報が、他のWebサイトやWebメディアに転載されていることに気づいた時は、次の3点を確認しましょう。
転載の許可を出した記録があるかどうか
転載の許可を出していなければ、無断転載であり複製権の侵害になります。転載先に連絡し、削除を依頼するか、あるいは次回以降は連絡するように勧告しましょう。
出典が記載されているかどうか
自社オリジナルのプレスリリースページのタイトルとリンク先URLが、出典として記載されているかどうかを確認し、もし記載されていなければ出典の記載を依頼しましょう。
内容が改変されていないか
原文の内容を改変しないことは、転載の大前提です。改変は違法になります。転載された際、オリジナルのプレスリリースから内容が改変されていないか確認し、されていた場合は原文に戻すように依頼しましょう。
Google検索における転載の注意情報

自社プレスリリースがWeb上で転載された場合、特にGoogle検索において、2つの懸念事項があります。それは「重複コンテンツと見なされる可能性」「自社サイトの評価が下がる可能性」です。それぞれについて説明します。
重複コンテンツと見なされる可能性
「重複コンテンツ」とはWeb上で同じ内容の文章が掲載されることです。
Googleでは無断転載された記事は、警告(ペナルティ)の対象としています。ペナルティの判断が下ると、検索順位が下がるといった措置がとられる可能性があります。
プレスリリースの転載は、同じ内容が掲載されているため、重複コンテンツと見なされる可能性がないとは言えません。
自社のページの評価が分散される可能性
Google検索の基本事項によると、自社サイトよりも転載先のサイトのほうが評価が高い場合、自社サイトの掲載ページの検索順位が下がる可能性があります。
検索順位が下がってしまうと、本来自社サイトで獲得できた閲覧数や評価が、転載先サイトに分散されてしまう可能性もあります。
これらはあくまで可能性ではありますが、プレスリリースを作る際、自社サイトのSEOを重視している場合は頭の片隅に入れておくと良いでしょう。
Googleにおける無断転載の対策
自社のプレスリリース等が無断転載されていることが発覚した場合、Googleに対し通報を行うことができます。
著作権保有者である場合は、Googleの「著作権侵害の報告」ページより著作権侵害による削除通知フォームを利用して申請を行いましょう。
無断転載は著作権法違反です。無断転載や盗用とみなされたコンテンツは、Googleの検索結果から削除される対処が行われます。トラブルが起きる前に早めの対応をしておきましょう。
転載のルールを確認し不要なトラブル回避を
他社の記事などを転載する場合は、「著作権者の許可」「出典の明記」のルールを徹底しましょう。転載作業のミスなどで盗用や著作権の侵害が疑われれば、社会的信用が失われてしまいます。
プレスリリースなど自社のコンテンツが転載された場合には、転載許可を出した記録があるかどうか、転載元として自社が明示されているか、リンク先が記載されているかどうか、原文のまま転載されているかどうかを確認しましょう。
自社のプレスリリースを各メディアに転載してもらいたい場合には、プレスリリース転載サービスの利用が便利です。
共同通信PRワイヤーでは、メディア向けのプレスリリース配信と同時に提携先メディアへの転載を行なっています。
また、メディア向けの配信は行わず提携サイトへの転載のみを行うプランも用意しています。
当社提携メディア約70サイトのうち、55サイト以上にプレスリリースの転載が行われます。転載サイトの内訳は以下の通りです。
- 報道機関のサイト
- 共同通信加盟社(地方紙)を中心とする新聞社のニュースサイト
- ポータルサイトのニュースコーナー
- そのほか有力な情報サイト
お申込み方法など詳しくは下記のページをご覧ください。
共同通信PRワイヤー「国内プレスリリース配信サービスのご案内」のページを見る
また共同通信PRワイヤーでは、広報・PR活動に役立つさまざまなサービスをご用意しております。詳細な資料を用意しておりますので、ぜひご利用ください。お申し込みは下記より可能です。
サービス資料ダウンロードページを見る