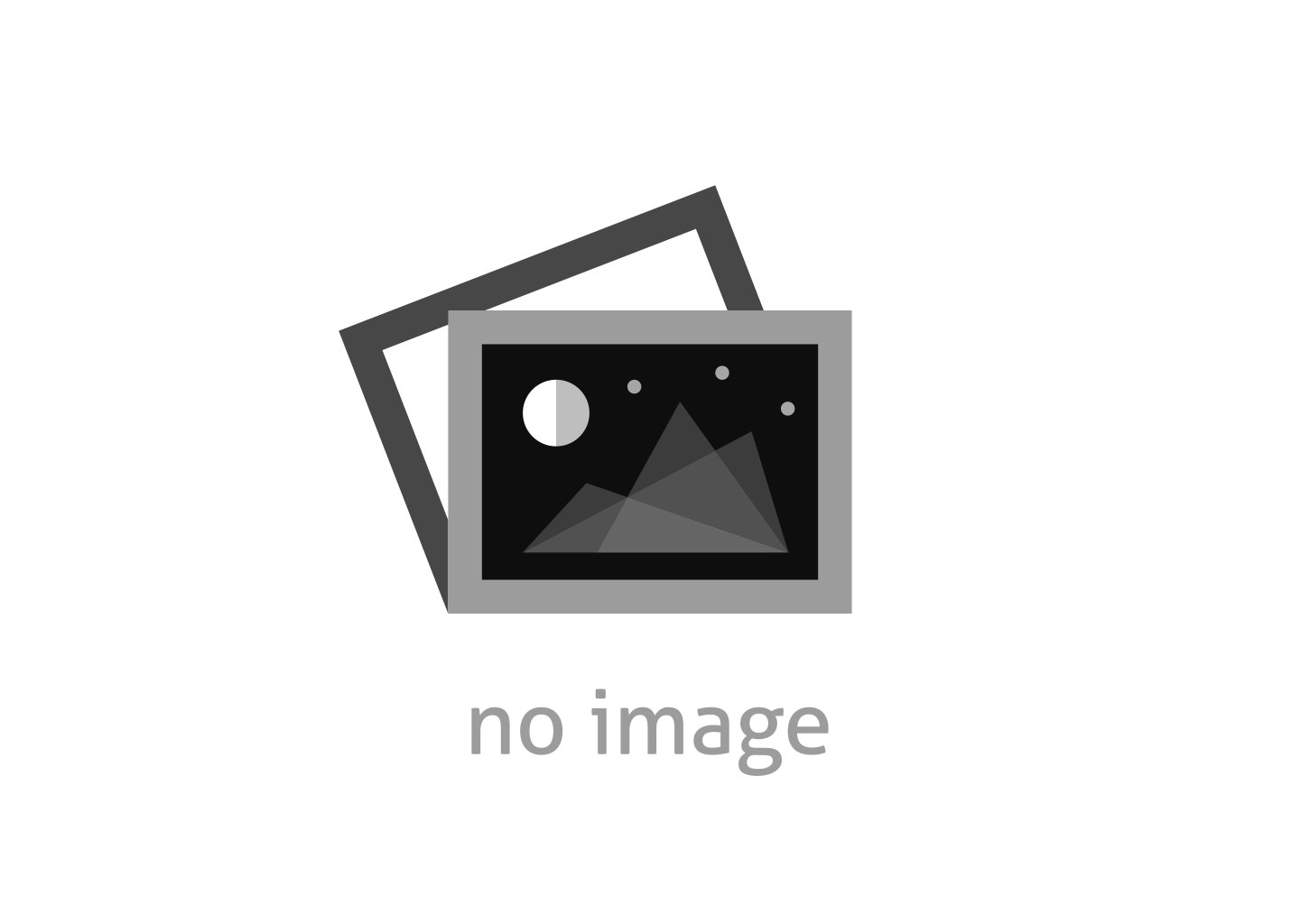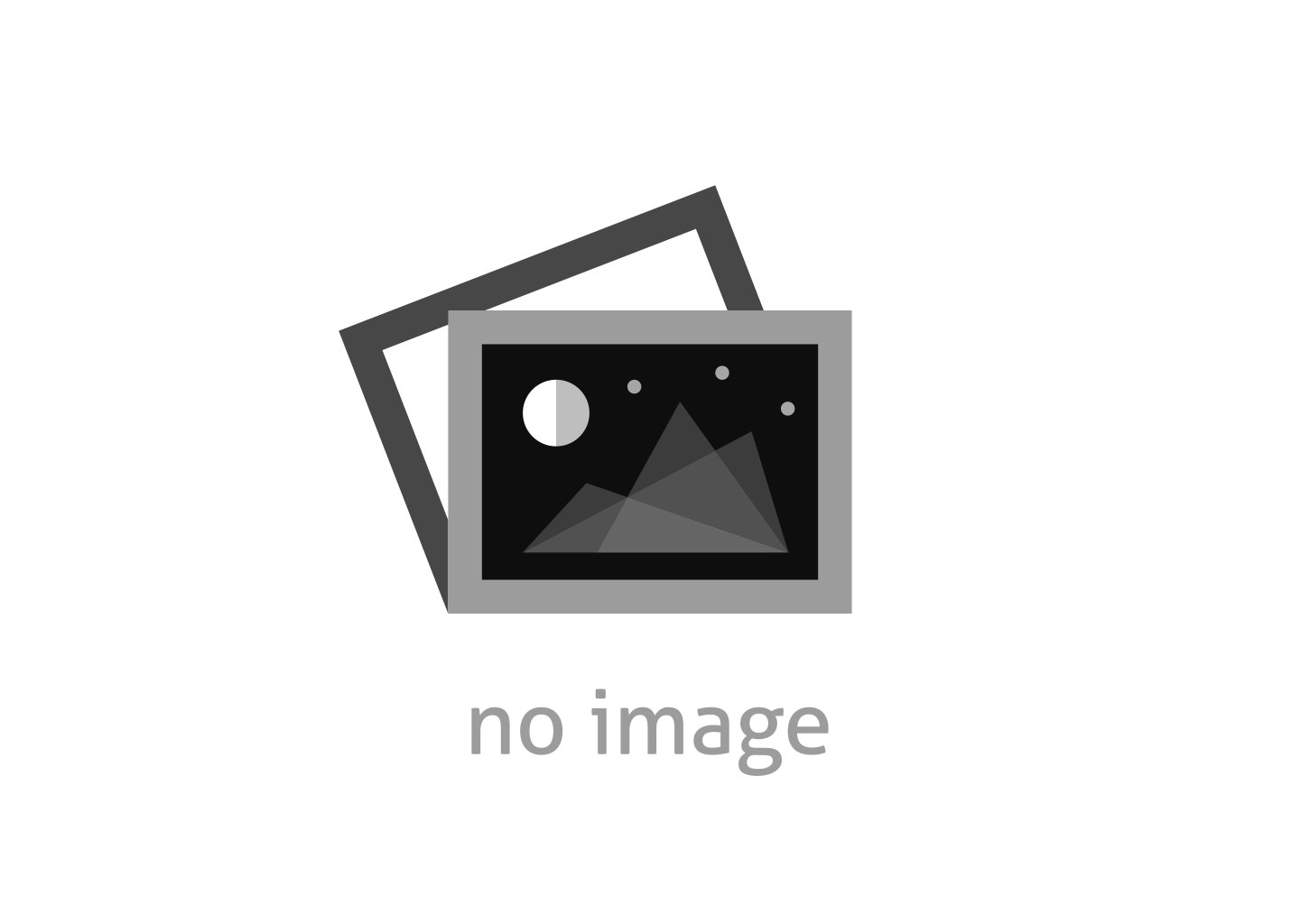堂島リバービエンナーレ2019 2019年7月27日ー8月18日 開催決定
2019年6月12日
堂島リバーフォーラム
堂島リバービエンナーレ2019 2019年7月27日ー8月18日 開催決定
堂島リバーフォーラムは、水の都、大阪の堂島川のほとりに2008年に誕生し、昨年開館10周年を迎えることができ、今年で11年目がスタートしました。みなさまにお支えをいただきながら美術、音楽など芸術文化の普及と発展に寄与すべく小さくとも輝く光を灯しながら一歩一歩、進んで参りました。今年で第5回目となる堂島リバービエンナーレには、2011年の第2回にもキュレーションをしていただいた飯田高誉氏をお迎えし、開催する運びとなりました。ジャン=リュック・ゴダールの最新映画作品『イメージ』の本からインスパイアされている本展は、唯一無二のビエンナーレになることと思います。
本展の開催に際し、ご尽力をいただいた多くの方々に改めて深謝を申し上げます。
第5回、堂島リバービエンナーレ2019
この夏、大阪、堂島リバーフォーラムで心よりお待ちしております。
2019年6月12日
堂島リバーフォーラム 古久保ひかり

開催概要
展覧会名:堂島リバービエンナーレ2019
シネマの芸術学 -東方に導かれて-
ジャン・リュック=ゴダール『イメージの本』に誘われて
開催期間:2019年7月27日[土]~ 8月18日[日]
会場:堂島リバーフォーラム(大阪市福島区福島1-1-17)
開館時間:11:00-18:00(入館は閉館30分前まで)
入場料:一般1000円/高校・大学生700円/小・中学生500円
特設サイト:http://biennale.dojimariver.com/
問合せ先: 堂島リバーフォーラム
電話番号: 06-6341-0115
主催・企画制作:堂島リバーフォーラム
アーティスティック・ディレクター:飯田 高誉
会場構成:イシダアーキテクツスタジオ株式会社
デザイン:長嶋りかこ(village®)
アーティスティック・ディレクター
飯田 高誉
(スクールデレック芸術社会学研究所 所長/国際美術評論家連盟会員)
フジテレビギャラリー(1980年〜90年)にて草間彌生を一貫して担当し作家活動歴のアーカイブ化を担う。東京大学大総合研究博物館小石川分館にて現代美術シリーズ(マーク・ダイオン、杉本博司、森万里子展)を連続企画。カルティエ現代美術財団(パリ)にてゲスト・キュレーション(杉本博司展、横尾忠則展)。「戦争と芸術—美の恐怖と幻影Ⅰ〜Ⅳ」展(京都造形芸術大学)シリーズ企画。コムデギャルソンの川久保玲の依頼によりアートスペース“Six”にて連続企画(草間彌生/橫尾忠則/デヴィッド・リンチ/森山大道/宮島達男/中平卓馬など)。第二回「堂島リバービエンナーレ:エコソフィア」展のアーティスティック・ディレクターを務める。京都造形芸術大学国際藝術研究センター所長、慶應義塾大学グローバルセキュリティ講座の講師などを務め、青森県立美術館美術統括監、森美術館理事を経て、現在、美術評論家連盟会員 スクールデレック芸術社会学研究所所長。 主な著作に「戦争と芸術-美の恐怖と幻影」(立東舎、2016)、共著に「アートと社会」(竹中平蔵・南條史生編著/東京書籍、2016)、「エッジ・オブ・リバーズ・エッジ──〈岡崎京子〉を捜す」(新曜社編集部 編、2018)など。
コンセプト
DOJIMA RIVER BIENNALE 2019
『シネマの芸術学_東方に導かれて_《X+3=1》』(註1)
「アートとは、現実の反映ではなく、その反映の現実性なのである」(註2)
「堂島リバービエンナーレ2019」展は、ジャン=リュック・ゴダールの最新映画作品『イメージの本(原題”LE LIVRE D’IMAGE”(英題︓THE IMAGE BOOK))』をインスピレーションとしている。「私たちに未来を語るのは“アーカイブ”である」(註3)と語るゴダールが、新撮シーンに絵画(TABLEAUX)、映画(FILMS)、テキスト(TEXTES)、音楽(MUSIQUE)を重層的にコラージュし、現代の暴力、戦争、不和の世界に対する彼の怒りを表明している。
この映画は、200年の歴史に関する省察であり、今日の世界についての洞察を与えている。そして、この世界が向かおうとする未来を指し示す5つのチャプター(註4)によって物語が構成されている。
「アウシュヴィッツの後で、詩を書くことは野蛮である」というテオドール・W・アドルノの言葉は、大戦後の知識人に大きな影響を与えた。ゴダールや本展出品作家のゲルハルト・リヒターにも少なからず影響を与えたと考えられる。システマティックな大量虐殺という事態が起きた後、詩的なもの、審美的なものを追求することについて倫理的に許容できないという糾弾は、ヨーロッパの審美的倫理観である真、善、美を激しく揺るがすものであった。アウシュヴィッツという空前の事件は、効率性を中心に据えたという意味においてまさに20世紀という現代を象徴する出来事だった言える。そしてこの野蛮の極致ともいえる事件は、まさに「文化」と見なされているその効率性から生じたものだった。アドルノによれば、文化とは野蛮の対極にあるものではなく、文化こそ野蛮との親和性を持ち得るものであることを認識しなければならないと述べている。そのような「文化」が引き起こしたアウシュヴィッツのあとで、文化の批判が根本的に為されないままに放置されるのであれば、アドルノが考える本来の意味の文化である「詩作」ですら、人間の活動からは最も離れたところにある野蛮さを体現しているといわざるを得ないのだ。
「堂島リバービエンナーレ2019」では、20世紀の記憶のアーカイブを前提にして、「飼い馴らされて」いないアートとは何なのかを問い掛けていくものである。市場で取引される画一化した大衆文化などグローバリゼーションによって金融資本主義的価値が重んじられ、真の意味での多様性が失われている現代において、本展覧会では、「文明」と「野蛮」を対立構造で捉えずに多様なテクネーと知性を用いて作品化しているアーティストの世界観を表象する作品を紹介することとなる。
また、「秩序」と「混沌」、「美」と「醜」、「生」と「死」、つまり、表層と深層の境界で画することではなく、人間に内在している感覚領域において、理性的な記憶に止まらない身体的記憶を呼び起こすことによって、「文明」と「野蛮」を対峙させることを表明していくことが、この展覧会のコンセプトとなる。
アーティスティック・ディレクター
飯田 髙誉
(註1)
「映画とは「X+3=1」である。もしX+3=1ならば、この「=」は「−(マイナス)2」です。
過去、現在、未来のいかなるイメージであれ、真の音や真のイメージが存在し始める第三のものを見い出すためには、消去することが必要である。「『X+3=1』とは、映画の鍵である」(ゴダール)
(註2)
Jean Luc Godard, David Sterritt (1998). “Jean-Luc Godard: Interviews”, p.29, Univ. Press of Mississippi “Art is not a reflection of reality, it is the reality of a reflection.”
(註3)
「私たちに未来を語るのは“アーカイブ”である」と語るゴダールが、新撮シーンにこれまでの絵画(TABLEAUX)、
映画(FILMS)、テキスト(TEXTES)、音楽(MUSIQUE)を巧みにコラージュし、現代の暴力、戦争、不和の世界に対する彼の怒りをのせて、この世界が向かおうとする未来を指し示す 5 章からなる物語。本作では、ゴダール本人がナレーションも担当している。昨年(2018年)5月に開催されたカンヌ国際映画祭では、映画祭史上初めて、最高賞【パルムドール】を超越する賞として特別に設けられた【スペシャル・パルムドール】を受賞した。前作『さらば、愛の言葉よ』(14)で、彼にしか創造し得ない新感覚の3D 技法で観客を驚かせたゴダール監督が今作では、枯渇することのないイメージと音を多用し、観客の創造力を縦横無尽に刺激されることであろう。
(註4)
「静寂にすぎない。革命の歌にすぎない。 5 本指のごとく、5章からなる物語」(ジャン=リュック・ゴダール)
参考文献
「啓蒙の弁証法」著者マックス・ホルクハイマー/テオドール・アドルノ
(原題:Dialektik der Aufklarung: Philosophische Fragmente)
「感覚の論理-画家フランシス・ベーコン論」著者 ジル・ドゥルーズ
参考引用文
「今日では文化がすべてに類似性という焼印を押す。映画・ラジオ・雑誌の類は一つのシステムを構成する。各部門が互いに調子を合せ、すべてが連関し合う。政治的に対立する陣営ですら自己宣伝の美的な様式は似たようなもので、ひとしく鋼鉄のようなリズムを謳歌している。大企業の華麗な本社ビルや商品展示場は、権威主義的な国であろうとなかろうと、ほとんど変りはしない。」(「啓蒙の弁証法」著者マックス・ホルクハイマー/テオドール・アドルノ、〈第4章、文化産業-大衆欺瞞としての啓蒙〉より)
ジャン・リュック=ゴダール (映画監督:1930〜)
20世紀の記憶を前提して、未来的ビジョンを提示しているヌーベルバーグという映画運動を起こした映画監督。高松宮殿下記念世界文化賞受賞。『勝手にしやがれ』『気狂いピエロ』など数々の名作を世に送り出してきたヌーヴェルヴァーグの巨匠。2018年5月に開催されたカンヌ国際映画祭では、映画祭史上初めて、最高賞【パルムドール】を超越する賞として特別に設けられた【スペシャル・パルムドール】を受賞した。
出品作家 (年齢順)
ゲルハルト・リヒター(ドイツ、アーティスト:1932〜)
ドイツの歴史的記憶をアーカイブ化している国際的な画家であり、「ドイツ最高峰の画家」と呼ばれ現代美術界を代表する巨匠。ドレスデン美術大学で美術教育を受けるが、59年にドクメンタ2を見るべくカッセルを訪れた際に、ポロックやフォンタナの作品などに感銘を受け、西ドイツへの移住を決意。61年にベルリンの壁が建設される直前にデュッセルドルフへと移住した。
60年代から70年代にかけて、新聞や雑誌に掲載された写真を元にしたフォト・ペインティングを制作し、ミュンヘンとデュッセルドルフで初の個展を開催、72年のドクメンタ5や第36回ヴェネツィア・ビエンナーレにも参加している。その後もアブストラクト・ペインティングなど多彩なシリーズを制作し続けるとともに、金獅子賞を受賞した97年の第47回ヴェネツィア・ビエンナーレや計6度のドクメンタ(5、7、8、9、10、14)をはじめ、多数の展覧会に参加、数々の個展を開催している。
日本でも、97年に高松宮殿下記念世界文化賞を受賞。
トーマス・ルフ(ドイツ、アーティスト:1958〜)
インターネットなど多様なメディアを題材にして写真作品化するドイツの現代写真芸術において重要な一翼を担う国際的なアーティスト。ドイツ、ツェル・アム・ハルマースバッハ生まれ。トマス・ルフは、アンドレアス・グルスキーやトーマス・シュトゥルートらとともにデュッセルドルフ芸術アカデミーでベルント&ヒラ・ベッヒャー夫妻に学んだ「ベッヒャー派」として、1990年代以降、現代の写真表現をリードしてきた存在。ルフは自ら撮影したイメージだけでなく、インターネット上を流通するデジタル画像からコレクションしている古写真まで、あらゆる写真イメージを素材に用い、新たな写真表現の可能性を探究。
フィオナ・タン(オランダ、アーティスト:1966〜)
ドキュメンタリーとフィクションの間を行き交いつつ、記録と記憶、見ること・見られることの関係を繊細に問いかける国際的なアーティスト。1966年プカンバル(インドネシア、スマトラ島)生まれ、現在はアムステルダム(オランダ)を拠点に活動。中国系インドネシア人の父とオーストラリア人の母をもち、オーストラリアで育つ。1988年よりアムステルダムに移住し、リートフェルトアカデミー、国立美術大学で学ぶ。横浜トリエンナーレ(2001、2005)、第8回イスタンブル・ビエンナーレ(2003)、ドクメンタ11(2002)、オランダ館の代表をつとめたヴェネチア・ビエンナーレ(2009)など多くの国際展に参加。東京都写真美術館においては、「第2回恵比寿映像祭 歌をさがして」(2010)で展示・上映両部門に出品している。
ダレン・アーモンド(イギリス、アーティスト:1971〜)
写真や映像、絵画など多様な表現様式によって自然現象や歴史的記憶を刻印していくことを作品化しているイギリスのニューウエーブの代表的アーティスト。ターナー賞候補になる。イギリス、ウィガン生まれ。ロンドンを活動拠点とし、ターナー賞(テートギャラリー)にノミネートされるなど国際的な活動を行っている。古より続く時間の流れや記憶に着目するアーモンドは、世界各地の古代遺跡や産業遺跡、自然を旅し、作品制作の重要なヒントとしてきた。1990年代より日本にも訪れ、京都・比叡山の千日回峰行を撮影した映像インスタレーション
《Sometimes Still》(2010)、茨城県の桜を撮影した写真シリーズ「Day for Night」(2006)などを手がけている。
佐藤允(日本、アーティスト:1986〜)
VOCA展や光州ビエンナーレに参加するなど国内外で活動を展開する注目の若手アーティストで絵画に関する考え方平面次元を超えて徹底的に探求。過剰、そしてオブセッショナルともいえるような、緻密な鉛筆の線描写。永遠に増殖し続けるかのように思える佐藤允のイメージは、描くことによって自らの存在、世界を捉えようとする作家の切実な試みを映し出しています。他人を理解することとはどういうことか、他人と心を繋がずに生きることはできるのか。これらの問いに突き動かされながら佐藤が描く、恋愛や性、生命、希望の溢れんばかりのエネルギー、そしてその一方にある不穏で深い闇、孤独、危うさ、恐れ。それらが調和し、あるいは不協和音を奏でながら、画面を埋めていきます。
空音央(日本/米国、映像作家:1991〜)/ アルバート・トーレン(米国、映像作家:1992〜)
空音央
映像や音楽作品によって民族や歴史的記憶を浮かび上がらせる現代感覚に満ちたニューヨーク在住のクリエーター。米国生まれ、日米育ち。コネチカット州ウェズリアン大学で映画と哲学を専攻し、それ以降、フリーランスの映像作家、写真家として活動。2014年より映像プロダクション会社 Good Baby Films を設立。2015年に北海道平取町二風谷で現代に生きるアイヌ民族を撮ったドキュメンタリー「Ainu Neno An Ainu」をアーティストコレクティブLunch Bee Houseと共同制作。その他にも短編映画、ドキュメンタリー、PV、ファッションビデオ、コンサートなどをプロデュース。写真と映画を交差するアート作品を制作。2017年にはワタリウム美術館で作品を展示、同年夏には石巻市で開催されているReborn-Art Festivalに参加し、短編映画とインスタレーションを制作。2017年冬、Talents Tokyo 2017に映画監督として参加した。
アルバート・トーレン
アルバート・トーレンはニューヨーク在住の映像作家。コネチカット州ウェズリアン大学で映画を専攻し、それ以降、短編やドキュメンタリー、ミュージックビデオ、コマーシャルのプロデュースや編集などを手がける。2014年より映像プロダクション会社Good Baby Filmsを設立。また、アーティストグループZakkubalanとしても作品制作し、2017年にはワタリウム美術館で作品を展示、同年夏には石巻市で開催されているReborn-Art Festivalに参加し、短編映画とインスタレーションを制作。2017年はIFPのMarcie Bloom Fellowとして選ばれた。2019年、アルバートがプロデュースした短編「The Rat」がサンダンス映画祭で上映される。
会場設計デザイン
石田建太朗(建築家 / イシダアーキテクツスタジオ株式会社代表)
1973年生まれ。ロンドンのArchitectural Association School of Architecture(AAスクール)にて建築を学び、2004年から2012年までスイスの建築設計事務所ヘルツォーク&ド・ムーロンに勤務。同社アソシエイトとしてペレス・アート・ミュージアム・マイアミ(マイアミ現代美術館)やトライアングル超高層計画(パリ)などのプロジェクト・マネジメント及びリード・デザイナーを務める。2012年に東京に拠点を移しイシダアーキテクツスタジオを設立。現在は、美術館などの建築設計からアートプロジェクトなどを手がける。「アートがあればII展」(2013)、「N’s YARD」(2017)、「積葉の家」(2018)。2016年より東京工業大学特任准教授。
グラフィックデザイン
長嶋りかこ(グラフィックデザイナー/village®主宰)
1980年11月11日生まれ。2003年武蔵野美術大学視覚伝達デザイン科卒業。2014年デザイン会社「village®」設立。アイデンティティデザイン、エディトリアルデザイン、サイン計画などグラフィックデザインを基軸に活動。主な仕事に札幌国際芸術祭(2014)、東北ユースオーケストラ(2016-)、『ASSEMBLE 共同体の幻想と未来』展(2017)、『アニッシュ・カプーアの崩壊概論』展(2017)ほか多数。
本プレスリリースは発表元が入力した原稿をそのまま掲載しております。また、プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願いいたします。
このプレスリリースには、報道機関向けの情報があります。
プレス会員登録を行うと、広報担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など、報道機関だけに公開する情報が閲覧できるようになります。
このプレスリリースを配信した企業・団体

- 名称 堂島リバーフォーラム
- 所在地 大阪府
- 業種 芸術・エンタテイメント
- URL https://www.dojimariver.com/
過去に配信したプレスリリース
第7回「堂島こどもアワード」絵画作品 募集スタート!
2025/7/20
第4回堂島こどもアワード 小学生を対象とした絵画作品を募集中です。
2022/8/8
第3回堂島こどもアワード 小学生を対象とした絵画作品を募集いたします。
2021/7/21
第2回 堂島こどもアワード開催決定
2020/5/5
堂島リバービエンナーレ2019 2019年7月27日ー8月18日 開催決定
2019/6/12
第1回 堂島こどもアワード -絵画作品募集中 作品応募期間は2018年1月31日まで。
2017/12/25